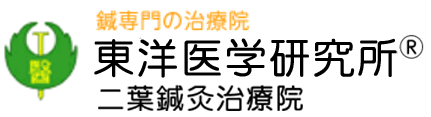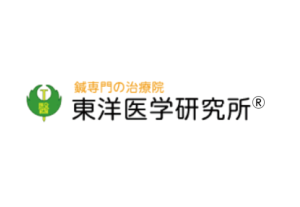令和6年度(公社)生体制御学会第5回Web講習会(愛知県鍼灸生涯研修会)に参加しました
令和7年2月2日(日)に令和6年度(公社)生体制御学会第5回Web講習会(愛知県鍼灸生涯研修会)に参加しました。
9:00~10:30
「糖尿病の薬物療法について②」(公社)全日本鍼灸学会認定指定研修C講座
愛知医科大学客員教授(神経内科)
岩瀬 敏 先生
本日は糖尿病について御講義頂きました。
「糖尿病とは、血液中のブドウ糖濃度が病的に高い状態を指す病名になります。血糖が高い状態が長期にわたると、体中の微小血管が徐々に破壊されていき、目や腎臓を含む体中の様々な臓器に重大な障害を及ぼすことが最大の脅威になります。よく起こる合併症では、神経障害、網膜症、腎症があります。
細小血管が障害されると、神経、目、腎臓に症状がでてきます。これを『糖尿病の三大合併症』と呼び、頭文字をとって“しめじ”と覚えることができます。
“し、しの神経障害”は手足がしびれ、体中の色々な神経が鈍くなります。
“め、めの網膜症”は視力が悪くなり失明に繋がります。
“じ、じの腎症”は腎臓の働きが悪くなって体に毒がたまってしまい、透析を受けることになります。
糖尿病の日常生活で気をつけることは、運動を定期的にする、麺類などではなく、米を食べる、よく噛んで食べる、食事の際に一番最初に野菜を食べる『ベジタブルファースト』があります。」と御講義頂きました。

10:40~12:10
第5章 使わない記憶は変容し、劣化する(思い出せない脳)
・不要だと判断された記憶は失われていく
・形を変えるシナプスが記憶の正体
・記憶は思い出すたびに変容する
→カンデル神経科学48章(シナプスの形成と除去)
49章(経験とシナプス結合の精緻化)
52章(学習と記憶:想起)
(公社)全日本鍼灸学会認定指定研修C講座
名古屋大学名誉教授
澤田 誠 先生
本日は、澤田誠先生が著された「思い出せない脳」の中から、記憶について御講義頂きました。
「感情が大きく動いたできごとを脳は優先して記憶します。意識して感情を動かしても記憶能力は上がり、特に怖い物事の方が記憶が定着しやすいのです。
MCH神経は寝ている時のレム睡眠中に、いらない情報を積極的に消去するように働きます。
記憶は「覚える」記銘と、「思い出す」想起に分けられます。
記銘には3つあり
- 符号化…新しい記憶形成の際に処理する過程のことで、情報に集中し、すでに確立されている記憶と関連付けることによって達成します。
- 貯蔵…新しく得た情報が長い間忘れないでいられる記憶として保持される記憶メカニズムを指します。その容量はほぼ無限と言われています。
- 固定化…一時的に保存されたまだ不安定な情報をより安定な状態に変化させる過程になります。」と御講義頂きました。